技術分野
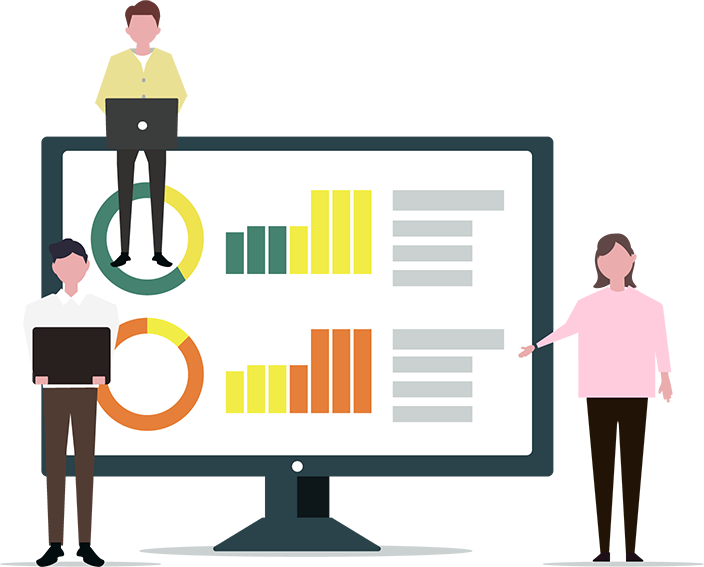
技術分野
弊社では、通信・コンピュータ・ビジネスモデルを最も得意としておりますが、
その他にも、電気、機械、製造装置等も数多く経験しております。
尚、化学(特に、有機化学)、バイオに関する調査、及び、意匠・商標調査は、
当事務所でのサービス提供は行っておりませんので、その点はご了承ください。
サービス一覧
| No. | サービス | 調査概要 |
|---|---|---|
| 1 | 無効資料調査 | 弊社が最も得意とする調査で、侵害可能性のある特許を発見、または特許を有する第3者から攻撃された場合に行う調査です。既に権利化された特許(権利化前を含む)を、権利無効とするための証拠資料を収集する調査です。尚、「無効資料調査」の他の表現として、「公知文献調査」、「特許性調査」、「先行技術調査」等と呼ばれる場合があります。 |
| 2 | クリアランス調査 | 「侵害(防止/予防)調査」等と呼ばれることがあります。自社の製品・サービスが第3者の特許権に侵害・抵触しているか否かの判断に基づき、関連する特許文献を抽出する調査です。 |
| 3 | 技術動向調査 | ある特定技術の特許文献を読み込んで解析し、技術・権利をエクセル化することでお客様オリジナルのデータベースを作成します。また、エクセル化したデータを用いてグラフを作成する(技術動向調査)ことも可能です。 |
| 4 | 出願事前調査 | 自社の特許出願前に、その特許が既に出願されていないか否かを確認する調査です。 |
| 5 | その他 | 権利状況調査等がございます。(但し、無料のデータベースで調べられることが多いです。) |
1無効資料調査
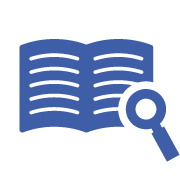
・その他の呼び方:先行技術調査、特許性調査、情報提供調査、公知文献調査
・英語標記:Invalid Search, Valid Search, Patentability Search, Prior Art Search
1-1概要
弊社が最も得意とする調査です。例えば、あなたの製品・サービスが第3者の特許を侵害していると訴えられた場合に行います。ある特許に対して、既に以前から知られていること(公知)を証明する資料・文献を調査・収集します。裁判でその資料・文献により特許そのものを無効とすることができます。
例:アルゼのパチスロ機特許により、裁判でサミーとネットに対して特許侵害が認められ、約84億円の賠償を命ずる判決がでました。しかし、サミーとネットが公知であることを証明することで、アルゼの特許を無効とし約84億円の賠償責任を逃れました。
また、その他のケースとして、他社の特許が権利化される前までに無効資料・文献を特許庁に提出して権利化を阻止する(情報提供調査)があります。また、自社の特許が権利成立後、本当に以前から知られていないか否か調査しておき(特許性調査)、自社の特許の権利の強さを測るものさしの1つとして同様の調査を行うこともごじます。
1-2調査手法、調査対象等
データベースを用いた機械検索がメインですが、特に、無効資料・文献調査では、大量の文献から探す必要がある場合が多々あり、文献を手めくりで調査するマニュアル調査もおすすめです。
対象とする文献は、日本特許、外国特許、一般文献(雑誌、論文)等、ありとあらゆる刊行物が対象となります。(日本語、英語以外の文献は、弊社では対応できませんので、その点はご了承ください)
尚、費用対効果を高めるために、対象とする資料・文献の種別の優先順位は、
日本特許(実用新案を含む) > 外国特許 > 非特許(一般)文献
とし、上記を同時にするよりは、「日本特許で見つからなければ、外国特許を調査する」というような手法をおすすめいたします。
但し、既に特許文献を調査している場合を除きます。
1-3報告様式
弊社では、無効にする対象の請求項を構成要件に分割して、構成要件毎に抽出した資料・文献に開示された部分とを対比して、解析を行います。報告書サンプルについては、こちらから。
2クリアランス調査
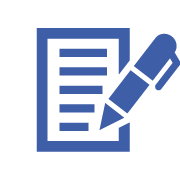
・その他の呼び方:侵害調査、侵害予防調査、侵害可能性調査
・英語標記:Infringement Search, Clearance Search, Freedom to Operate Search, Freedom to Practice Search
2-1概要
あなたの製品・サービスを提供する(開発する)前、他社の特許権利を侵害している可能性のある特許文献を調査・収集するものです。
尚、クリアランス調査において、「完璧な調査」は不可能であることをご了承ください。あなたの製品・サービスの提供前の「健康診断」であることをご理解ください。より精密な「精密検査」であるように尽力いたします。
2-2調査手法、調査対象等
機械検索がメインとなります。極力様々な観点から調査するようにし、各観点を絞り込んでノイズが少なく網羅的に調査を行います。また、権利消滅が確定したものを除いて、権利が存続しているもの、または権利化される可能性があるものに絞り込んで調査を行うことで、より精度良く調査することも可能です。
尚、海外での製品・販売の場合は、各国での調査が必要となります。弊社では、日本語、英語以外の文献には、対応しておりませんのでその点はご了承ください。
2-3報告様式
ご依頼の際に提供いただいた資料、またはお打ち合わせに基づき製品を技術要素に分割して、この技術要素毎に権利に抵触するか否かを調査いたします。特に、上位概念で記載された権利範囲の広い特許を抽出するようにするためです。報告書サンプルについては、こちらから。
技術要素例
- 対象サービス
- 広告等に記載された二次元コードをスマートフォンで読み取らせ、スマートフォンでオンラインショッピングのサイトに接続させるオンラインショッピングシステム。
- 技術要素
- ① ネットワークを介して接続された携帯端末とサーバとを備えたシステムにおいて、前記携帯端末は、
② 所定の画像を取り込むための画像取り込み手段と、
③ 前記画像は、二次元コードであって、当該二次元コードをURLに変換するためのURL変換手段と、
④ 前記URL変換手段によって変換された前記URLに基づき、サーバへ接続するサーバ接続手段と、を具備し、前記サーバー
⑤ オンラインショッピングのためのWEBページを前記携帯端末に提供するWEBページ提供手段と、を具備することを特徴とする。
- 効果
- 仮に「二次元コードをURL変換する」のみが権利化されていた場合に、端末がスマートフォンであるか否か、またはその用途がオンラインショッピングであるか否かに関わらず、抵触すると判断できます。このように技術要素毎に対比することで、読み漏らしがちな権利範囲の広い(上位概念)を漏れなく抽出することができます。
3技術動向調査
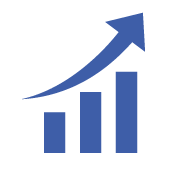
・その他の呼び方:特許出願動向調査、パテントマップ、特許マップ
・英語標記:State of the Art Patent Search, Patent Map
3-1概要
ある特定の技術分野等の特許文献を広く収集して、特許文献を解析して整理するものです。特に、整理し結果をエクセルデータに展開することで、お客様固有のデータベースとすることができます。この調査を実施することで、お客様の知的財産戦略、製品開発にご利用いただければ幸いです。
3-2調査手法、調査対象、報告形式
機械的な集計によりご報告する場合がございますが、弊社で得意とするのは、技術区分付けです。1件、1件読み込んでお客様ご指定、または弊社提案の技術区分を付与していきます。付与した後、エクセル形式で納品いたしますので、お客様固有のデータベースとして使用することができ、また、エクセルの機能でグラフ等の資料が簡単に作成でき、所定の技術の変遷等を解析することができます。尚、権利状況、新規に発行された特許出願等を定期的にご報告してデータベースを更新することも可能です。
尚、幅広く取得するということで、お勧めは、特許分類を全て見る方法です。ノイズ・漏れの少ない網羅的な調査を行うことができます。
- 例:ポイントシステムについて調べたい
以下の2つの分類を用いる
・非現金による処理に特徴を有するキャッシュレジスタ。(FI記号:G07G1/12,321L)
・販売促進方法に特徴を有する電子商取引。(FI記号:G06F17/60,324)例えば、
サービススタンプ→金券を自動発行→リライトカードを用いた処理→サーバで顧客ポイントを管理する→管理したポイントを他のポイントに交換する/自動でポイントの換算率を調整する
等の技術の変遷がわかる。また、エクセル形式でのご報告で、どのような特許が権利化されているか直ぐにわかります。上述のエクセルのサンプルについては、こちらから。
4出願事前調査

4-1概要
お客様のアイデアを特許出願したいと思いたった場合、その前にそのアイデアが既に特許出願なされていないか否かを調査するものです。
この調査の効果としては、出願費を抑えることができる、抽出された先行技術文献からアイデア権利化のための対策を練ることができる、審査請求費用を抑えることができるが挙げられるかと思います。
4-2調査手法、調査対象
検索は、機械検索のみで、概ね100件程度に絞り込んで調査いたします。
4-3報告形式
お客様のご予算に応じて、関連する文献のみを送付する、関連すると思われる記載箇所を明示する、さらに、関連度を付与する等いくつかの報告形式がございます。報告書サンプルについては、こちらから。
5その他
その他、以下のような調査がございますが、いずれもご自身でも調査可能であり、必要に応じて調査手法をご教示いたします。
また「こんな調査はできますか?」等、何かございましたら遠慮なくお問い合わせください。何らかのご提案をさせていただきます。
尚、お問い合わせについては全て無料で、お見積もりの後の発注指示を受けた場合にのみ費用が発生するのでご安心ください。
| 審査経過調査 | 特許庁の審査はどこまでいっているのか、権利化されそうかどうか等の調査です。 |
|---|---|
| 権利状況調査 | 権利化後年金が支払われて権利が維持しているか等の調査です。 |
| パテントファミリ調査 | ある特許の外国出願の有無についての調査です。 |